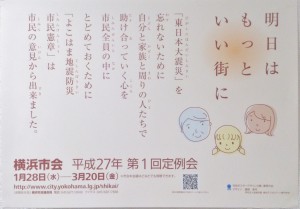人生のエンディングを学び、決めて託すーそれが大人のたしなみ。 おひとり様も家族がいる人も納得のいく終末期を送るには。と題して、横浜でもご縁のある(株)OAGウエルビーR代表取締役、黒澤史津乃氏が月刊潮6月号に寄稿をされていました。以下内容の一部要旨です。
近年、「おひとりさま」という言葉を耳にします。終活(人生の仕舞い支度)の業界では、「身寄りのない高齢者がどうエンディング期を迎えるか」というニュアンスで「おひとりさま問題」等といわれますが、「おひとりさま」に限った話でなく、誰もが人ごとではいられないと、まずは綴られています。人生には必ず家族がいる場合であろうと、なかろうと「自分では正常な判断ができない状態になる」タイミングが来る。認知症や病気、又は亡くなった後の期間はもちろんです。日本では、自動的に「家族」が意思決定の主役なります。現代は、家族がいあたとしても縁遠くなっていたりするケースも多くみられ様々な問題が生じます。
子どもが元気だけど仲が悪くて疎遠の場合や、遠方在住で病院に駆けつけることのできない場合、親の側が子どもに迷惑をかけたくないと遠慮する場合等も「おひとりさま」と同じ状態となってしまいます。これ迄、「困った時は家族にを頼れ。家の外には迷惑をかけるな」とういう事で価値観においても制度においても「家族」が社会の最小単位になってしまっています。その淵源の一つは、高度成長が終わった1970年後半、大平内閣で進められた「日本型福祉社会」という構想にあります。
「日本型福祉社会」という構想では、家庭を社会の最も大切な中核として、家庭での「相互扶助」を提唱。公助はあくまで自助や家庭福祉を補完する形として捉えていました。この「日本型福祉社会」が成り立っていたのは結局、母や妻(嫁)という女性が専業主婦として家庭に籠り、家族のケアを一手に引き受けていたからです。
80年代には、男女雇用機会均等法が成立する一方、専業主婦の優遇政策が多く実施されました。女性も総合職として男性と同様に働けるようになったのものの、あくまで専業主婦を優遇して「女性が家庭内の自助を担う」という制度を維持してきました。 
しかし、家族任せの社会はもはや限界を迎えつつあります。1990年代後半以降、日本では就職氷河期があり、非正規雇用が増加、共働きも当たり前になりました。生涯未婚率が急増する一方、夫婦の三組に一組は離婚するようになっています。そして老々介護や長期ひきこもり、ヤングケアラーなど家庭のなかで見えてこなかった難題が社会問題が顕在化しました。日本型福祉社会が想定していた家族像は既に当たり前のものではなくなっており、家族だけで親や祖父母の介護を担うのは、かなりのリスクとコストを伴うものになっているのです。
「呼んだらすぐに来てくれる家族」がいない高齢者が終末期を迎えた場合、現場では、ケアマネージャーや民生委員、地域のボランティアや医師、看護師など、医療・介護従事者が、対症療法的にその場で膨大な「シャドウ―ワーク」を行って対応しているのです。(実際、私もこの現状をソーシャルワーカーの責任者の方に、お聴きする機会もありましたが、大変なご苦労が伴っています。)「シャドウ―ワーク」で、無理に無理を重ねて、どうにかやりくりしているのが実情です。
社会福祉のビジョンが限界を迎えているからこそ、これからは、「家族だけが介護や世話の担い手でない」「社会の最小単位は家族でなく個人」という価値観への転換が必要です。(同:黒澤史津乃氏)
横浜市では、横浜市民の人生の最終段階の医療等に関する意識調査を行い発表もしています。⼈⽣の最終段階をどう過ごしたかを元気なうちから考え、希望する医療・ケアについて⼤切な⼈と話し合う、⼈⽣会議(アドバンス・ケア・プランニング:略称ACP)の啓発を⾏っています。市⺠が⼈⽣の最終段階の医療等について、どのように情報を得て、どのように話し合っているのか等を把握し、今後の施策に役⽴てていくことを⽬的とした調査です。また、横浜市『⼈⽣会議』短編ドラマ等を作成。この課題に対して公明党横浜市会議員団として視察や勉強会も行い横浜型課題解決のモデルの形成を目指しています。