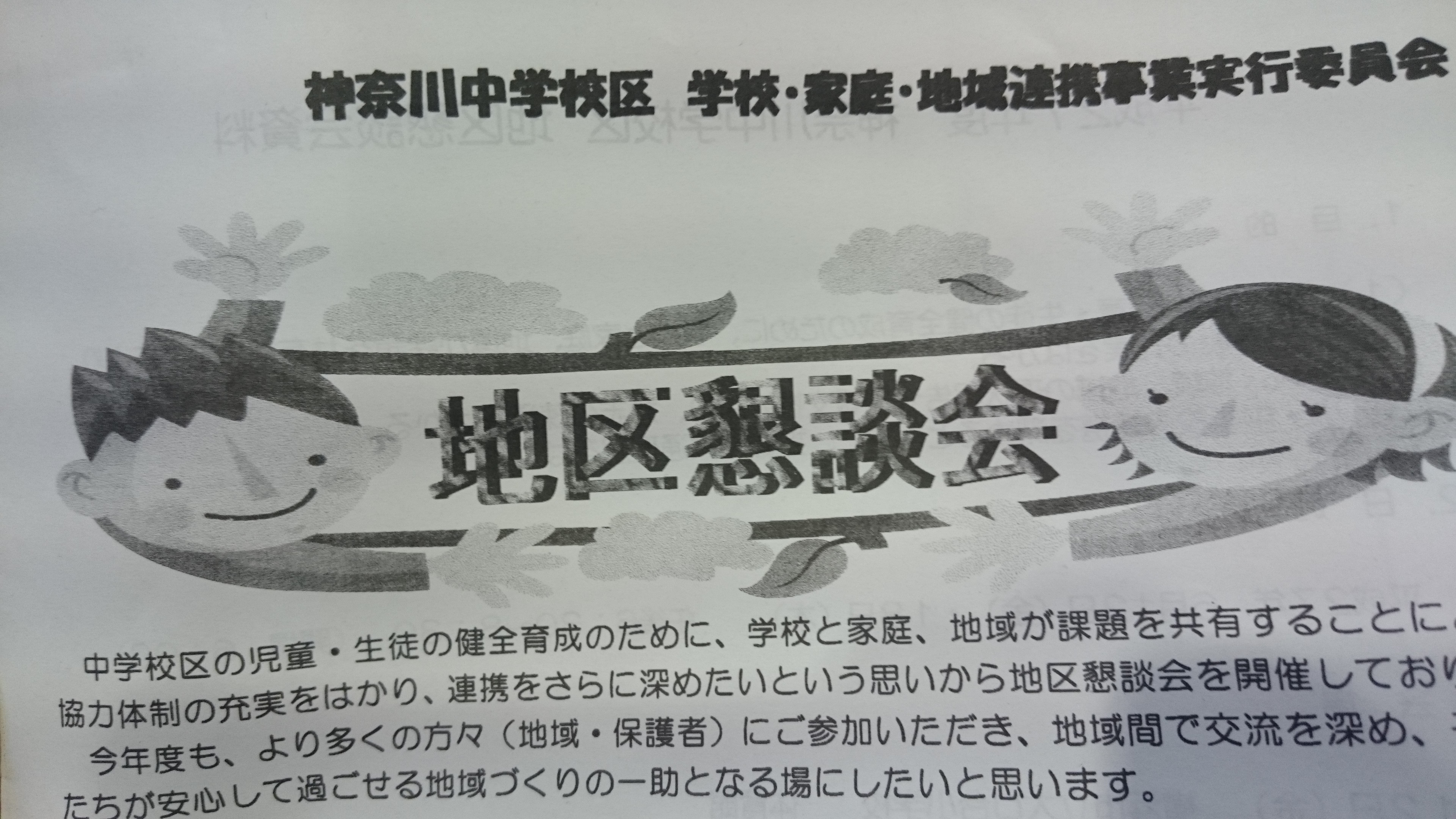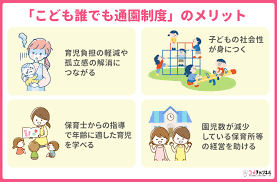「地域みんなで子どもを育てる」という合意づくりが必要です。コミュニティづくりと地域のネットワークづくりによって地域で顔見知りが増えることで、子育ての基盤としての「地域」が強化されます。
あえて「地域の子育て力」を言う背景には、子育てに自信が持てない親の増加、子どもに自信を持って生き方を示すことができる大人の減少、地域社会の交流の希薄さなどが原因と考えられる事件や社会問題が背景にあります。
また、子どもが育つためには、親を含む大人は共に育たなければならず、大人自身も学んでいくことが不可欠です。
また、「地域の子育て力」の向上は10年、20年という長期的観点を持って取り組まねばならないことは言うまでもありません。「地域の子育て力」により育てられた子どもが10年、20年後に親になり、同じサイクルを繰り返し、好循環で継承されることにより、地域全体も向上していきます。
地域住民間の交流が深ければ地域には活力が生まれ、子育てしやすい環境が生まれるでしょう。地域社会が「地域みんなで子どもを育てる」姿勢を持つためには「地域の子育て力」を住民が共通認識として持ち、交流がなされる社会にすることが必要です。
そのためには消極的に受け身に属している地域社会を、自分にとって、またより良い子育てをするために、地域住民の相互関係を発展させるための参加の場として、意識的に変えていくきっかけが欠かせません。
そのきっかけとしては、地域社会の中で自然に醸成された人間関係の中で解決できるもの、サークル活動等への参加により解決できるもの、制度をつくり有資格者が対応するものなど何段階かの方法が考えられます。
これらは、公園デビュー、保育園・幼稚園・学校での交流と進んでいく子どもを媒介とした人間関係を越え、親も学び子どもと共に育っていくこと(共育)を一歩進めていく手助けとなります。
(横浜市における「子育て教育について」第26期横浜市社会教育委員会議・提言より)
地元の中学校区の 地区懇談会に参加させていただきました。児童生徒の健全育成のために、学校と家庭、地域が課題を共有することにより、協力体制の充実をはかり、連携を深めたいとの思いで開催がされています。
昨日は、「今の子どもの支え方 ~変わったことと変わらなかったこと~」とのテーマで、学校カウンセラーの方より講演、グループ討議&情報交換、まとめ報告との流れの研修懇談会。
出席も、町内会・自治会役員・地域・保護者・校外役員・小中学校職員とまさに、学・家・地の連携での開催でした。
家庭の声として、インターネット・スマホ・SNSとの関わり、依存への心配が多く聞かれたのは、まさに時の声。
講演の結びにありましたが、何があっても、どんな子どもでも・・・信じ 大切に思い続け 「かけがいのない子だよ」と言ってあげること そして、悪いことは真剣に叱る。
そうした家族の存在が、(また地域の身近な関わりも含めてと思っていますが)大切です。