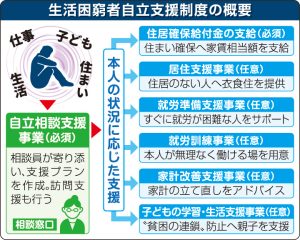「つながりが生み出すイノベーションセクターと創発する地域」とのテーマで、大阪公立大学の菅野拓准教授を訪問しました。
今年9月に開設された大阪公立大学の森の宮キャンパスを訪問。森ノ宮キャンパスは、「知の森」としてイノベーション・コアを牽引。 良好な交通アクセスかつ大阪の東西都市軸の東部重要拠点である 森之宮に立地するメインキャンパスとして、2025年9月に開設しました 。
今期所属する横浜市会特別委員会、「市民活躍・地域コミュニティ活性化特別委員会」のテーマとして、「つながりが生み出すイノベーションセクターと創発する地域」について菅野准教授にお話しをお伺い致しました。
菅野准教授が嘗て書籍でも紹介されていました「ネットワークを可視化する」(やっかいな問題はみんなで解く/世界思想社)するという事が、私も大切に思っています。2011年の東日本大震災においてサードセクターがやっかいな問題に対応してきたと言われます。ある調査でリストアップできただけでも約1400以上の組織が、震災で生じた様々な社会課題に対応していた。その活発さや効果は被災地の中でも地域差があり、それは社会ネツトワーク、人と人のつながりが、これを規定する重要な要因となっいてるようであったとされます。
菅野准教授の独自のサードセクターの社会ネットワークの分析では、その構造は震災前からずっと「べき乗則」があてはまり、「スケールフリー・ネットワーク」であった。「べき乗則」とは、地震の規模と発生頻度の分布、収入の分布、人口規模別の都市数の分布など、ごくわずかな大規模なものと、その他多くの小規模なものからなり、様々な自然現象にみられる分布特性であったとされます。
ほとんどの人は一人からしか指名されていないが、ごくたまにたくさんの人から指名される人がいて、ほんの一握りの人が多くの人から信頼され、ネットワークの「ハブ」となって様々な情報をやりとりする中継点となっていました。ネットワークのハブとなる人物は、やっかいな問題を扱う際、セクターや組織を超えて形成されたネットワークを通じて、問題を明確化するとともに解決のための知識や資源を動員する。(菅野准教授)
ネットワークというメカニズムは、ハブとなる人物を通じてやかいな問題にアプローチし、解決を生み出す。このような解決策の生み出し方のパターンが一般的なものだとの認識が、現在の社会にない。そのため別のパターンを採用する。
ネットワークというメカニズムを働かせる重要分子はハブとなり人物です。ネットワークという解決パターンを社会実装するために最も重要なことは、ネットワークの要となるハブ、つまり人と人をつなぐ人の取扱いを変える事。言葉を変えるならばハブを「プロ」として理解し取り扱う事が大切です。
ハブとなる人物は現に、優秀なコーディネーター、優秀なプログラムオフィサー、優秀なロビィスト、優秀なCSR担当者、優秀なリサーチ・アドミニストレーター等として、ハブを担う人は、社会に存在。高等教育機関や政府においても、この様な人物を育てようという試みが機運が上がってきています。しかし、まだ階級組織や市場で求められる人物ほどには、育て方や組織における位置づけ方等、ネットワークのハブの扱い方を理解できていない。この数十年、やっかいな問題に試され続けていますが、効果的な解決の糸口はここにある様に思えてならない。(同)
横浜市の多様な市民力、ネットワークをつむぐ、人と人を繋ぐ人の作用、ネットワークを可視化する。課題先進都市ともいえる横浜には、多くの横浜を愛して行動するひとが多くいます。ネットワークを可視化し、コーディネートする人が重要という事に思います。