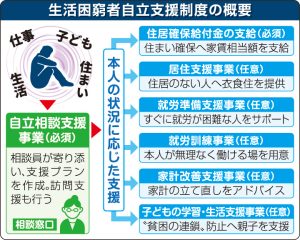2011年のKIITOの準備室時代から運営に携わり、社会課題解決型のデザインセンターを標榜し、「みんながクリエイティブになる、そんな時代の中心になる」というスローガンを掲げて、様々な種(プロジェクト)を作り出してきた永田宏和センター長のもとへお伺いしてお話をお聴きしてきました。
KIITOでの実践では、「ちびっこうべ」や「BE KOBE」「男・本気のパン教室」「チャイケモチャリティマルシェ」「date.KOBEプロジェクト」「ふれあいオープン喫茶」「仮設のピザ窯のある公園」など、たくさんの種(プロジェクト)が生まれ、そこに多くの人たちが関わり、様々な化学反応を起こしながら、発芽し、根を張り、育っています。
永田センター長のメッセージ「みんながクリエイティブになる。そんな時代の中心になる。」(KIITO:HP掲載)では、
「神戸で暮らす人や働く人。子どもや、若者や、大人たち。そんなすべての人が集まり、話し、つぎつぎに何かを生みだしていく場所。それがデザイン・クリエイティブセンター神戸です。一部のアーティストやデザイナーだけでなく、さまざまな人や世代が交流し、そこから生まれるアイデアや工夫で新しい神戸をつくっていく。
その「実践」が積み重なれば、じぶんの街への愛着が増し、街そのものにも個性が生まれ、やがては神戸の経済もより元気になっていく。人がクリエイティブになること。街がクリエイティブになること。この場所が、そのための中心地となること。近い将来、日本や世界のまちづくりのお手本になるために、神戸三宮の地で、かつてない試みが動き始めています。」とあります。
KIITOの活動理念(フィロソフィー)では、風、水、土、そして種の話を掲げています。この基本理念は、地域活動やまちづくり活動の支援を行う際に「三つの立場」=風、水、土、が必要であるとしています。それぞれ立場が担うべき役割があり、地域の人達がお互い仲良く、生き生き暮らす元気なまちになる「地域豊饒化」にするには、加えて「強度のある活動(強い種)」が必要になるという考え方があります。
そして、「三つの立場を担う人」については、以下の様になります。「土の人」は、「土」は動かない存在。そこに居続ける存在なので「地域住民」です。そして「種=活動」は、地域には昔から様々な「祭り」「餅つき」「防災訓練」等の活動があります。
高度成長経済期以前は、「土」は豊かでした。コミュニティーが豊かで、「土」にも養分もしっかり含まれた状態でした。「土」が豊かであれば、どんな「種」を植えても自然に芽が出て、根を張り、成長し果実を実らせ、種を落とし、また芽がでる。「種」は、誰の力を借りなくても自己完成的に機能し続ける事が出来たのです。
しかし、現代は「土」は枯れてしまっています。水分も養分も含んでいません。地域コミュニティーが希薄で、倒壊している地域も多くなっています。すると長年の自生していた「種」も立ちいかなくなります。芽が出ない、根を張らない、言い換えれば、誰も手伝わない、参加しないという状況に陥り、その状況が長く続けば「種」はいずれはなくなってしまいます。
そして、地域から「祭り」や「餅つき」が姿を消していきます。その危機的な状況を打破する救世主として期待されるのが「風」の人と言われます。風の役割は、乾いた「土」で芽が出なくなった古い「種」を品種改良して強い「種」として、風に乗せていろいろな地域に紹介していくことです。地域に住んではいないけど、外にいる専門家となります。
この強い「種」をつくれる存在を、今まさに社会は求めています。日本のあらゆる地域が「風の人」欠乏症で、強い「種」を切望しています。但し、「風の人」は強い「種」を携えて紹介に来ますが、その地域にずっと留まり、支援をし続け、その成長を見守る事はできない外の人です。
「風」が運んできた強い「種」に水をやって育ててくれるサポート役が必要になります。それが「水」の人になります。「水」人は地域愛にあふれ、地域活動をしているまちの応援団となります。具体的には、町内会、PTA、NPO等のメンバー、自治体の職員、ボラティアの大学生などで、多様な「水の人」が地域には存在し、活動しています。「水」はまだまだ地域に存在し続けていて、活動をしています。「水」いるが「風」がいない、強い「種」がない。これが今多くの地域や社会が抱えている切実な課題であると永田センター長は語られています。(やっかいな問題はみんなで説く:世界思想社) 
こうした状況を踏まえて、KIITOがやるべきことは、「風」の人を育てることであり、「風の人」のスキルである強い「種」のつくり方を多くの「水の人」に伝授する事ではないかと考えで活動を展開しているとの事です。横浜市には多様な、横浜を愛する「ハマっ子」がいます。市民力も培ってきました。特別委員会のテーマ(付議事件)である“誰もが居場所と役割をもち、いきいきと生涯活躍できるまちづくりやコミュニティーの活性化”に関する事の視点から、今一度、横浜を見つめ続けたいと思います。