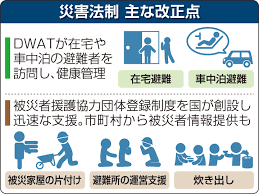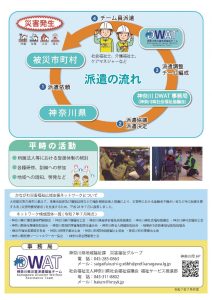令和8年度予算案について、公明党横浜市会議員団を代表して、斉藤しんいち団長が本会議質疑を行いました。その中で、防犯条例と新たな防犯対策についても取り上げました。昨年1月、公明党横浜市会議員団は、自由民主党横浜市会議員団とともに山中市長に対し、「防犯対策の強化を求める要望書」を提出したこと等も踏まえての質問です。質疑答弁の要旨は以下の通りです。
●昨年の予算代表質疑において、「防犯計画の改定と、その実効性を高めるために防犯条例の制定が必要である」と提案しました。その後、条例骨子案の策定やパブリックコメントの実施など、提案を真摯に受け止め、着実に進めてこられたことを評価しております。また、新たな中期計画の素案においても、政策群1「毎日の安心・安全」に防犯を位置付けるなど、防犯対策に対する強い思いが感じられます。そこで、
【質問】新たな防犯条例と中期計画の関係について、市長にお伺い致します。
【市長答弁】新たな条例は市の責務並びに市民の皆様や事業者の皆様の役割を明らかにして犯罪の防止並びに防犯意識の向上などを図るための基本姿勢を示すものとして現時点では計画しております。中期計画は一方で市民生活の安心・安全を最重要のテーマの一つとしてそして、それを具体的に実行していくため取組をまとめております。条例と中期計画とを連動させて防犯対策を推進していくことで安全で安心なまちづくりの実現に向けて取り組んでまいります。
●私も条例の骨子案を確認しましたが、内容としては、本市の防犯対策における基本理念を示す色合いが強い印象を受けました。そこで、
【質問】条例の実効性をどのように確保していくのか、市長にお伺い致します。
【市長答弁】新たな条例では防犯のまちづくりにかかる基本的な計画を定めることとしております。その目的で「横浜市防犯のまちづくり推進プラン」の策定を進めております。新たなプランでは「暗がりの解消」に向けた夜間照度の充足に取り組むことやご要望の多い地域での防犯カメラの設置率を100%とする等の成果指標を定めて条例の実効性を確保してまいります。
●防犯対策に関しては、新たな条例の制定だけでなく、新規事業が打ち出されるなど、私も大変注目しています。その中のひとつである「暗がり」の解消について、これまでも我が党は、地域に必要な場所において街の灯りを確保していくことが重要であり、場所や条件によっては太陽光発電式のLED灯が有効であると提案してまいりました。通勤・通学で市民の皆様が利用する道路などには、しっかりと灯りを確保することが、安心と安全につながるものと考えます。そこで、
【質問】「暗がり」の解消を迅速に進めていくべきと考えますが、市長のご見解を伺います。
【市長答弁】市民の皆様に対する防犯に関するアンケートにおきましても夜の暗がりに対する不安すなわち、夜間の屋外照明の設置に関するご回答が最も高いという結果でありました。こういった状況、市民の声を捉えて防犯灯の位置情報から暗がり箇所を見える化したGISマップを作成いたしました。そのマップを元にどこに防犯灯を設置したらいいのかあるいは移設したらいいのか、効率的に検討そして、実行に移してまいります。また、電柱などが無い場所などでは太陽光発電式のLED灯の設置などによって「暗がり」の解消に迅速に取り組んでまいります。今後進めていく過程で「ここの暗がりを解消してほしい」という個別の御要望も多く出てくると思いますしまた、一方でここは明るすぎるというようなご意見も逆に出てくるのではないかという風に思います。地域にお住まいの市民の皆様に安心・安全を実感していただくための夜間照度の向上に向けた、市役所としての取組になりますので地域の皆様のご意見を丁寧にお伺いし、市内全域の夜間照度の向上に取り組んでまいります。
●令和8年度の防犯対策における新たな事業のひとつとして、安心して荷物を受け取れる環境づくりを進めることを目的に、宅配ボックスの設置支援に取り組むとされています。この取組は脱炭素にも寄与することが期待されます。是非、多くの市民の皆様に支援制度をご活用いただき、宅配ボックスの普及につながることを期待しております。そこで、
【質問】宅配ボックスの設置支援の今後の展開について、市長にお伺い致します。
【市長答弁】市民の皆様の防犯意識の高まりや荷物を対面で受け取る際のご不安また、なりすまし強盗への警戒感が増していると承知しております。国が策定した「国民を詐欺から守るための総合対策」においても宅配ボックスの支援が位置付けられております。また、副次的に宅配ボックスを設置することによって再配達をする際のトラックのCO₂排出の抑制効果にもつながるという風に考えております。利用状況や効果の検証を通じて今後の幅広い展開を進めていきたいと考えております。
●また、本市では、条例制定を機に、「安心を実感できる・安全を届ける“スマート防犯シティ横浜”」という新たなキャッチフレーズを掲げ、事業の展開を図るとされています。この姿勢からも、防犯対策を一層前へ進めようとする強い意欲が感じられます。そこで、
【質問】スマート防犯シティ横浜に対する市長の意気込みを、お伺い致します。
【市長答弁】まず、キャッチフレーズを評価していただいてありがとうございました。市民局のほうで提案してもらったものなのですが、まさに今後横浜の防犯がどこに向かうべきかを端的に表しているキャッチフレーズだと思っております。現在、策定を進めております「横浜市防犯のまちづくり推進プラン」のもとで、暗がりの解消、そして特殊詐欺に合わないための啓発注意喚起、そして、先端技術やデータの活用によるこどもの見守り強化に取り組んでまいります。スマート防犯シティ横浜の取組を推進して犯罪を未然に防ぎ市民の皆様に安心の実感を届けてまいります。(要旨)