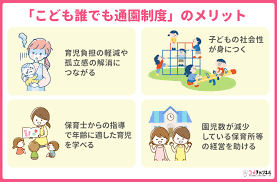市民の皆さんの安全で快適な暮らしを実現するための拠点施設として、消費生活相談、消費生活情報の提供、講座などの啓発事業等の消費者活動の支援などを行ってるのが横浜市消費者総合センターです。
消費者から寄せられる消費生活相談(商品やサービス等の購入・契約から発生する苦情や消費生活に関する問合せ)に、専門の相談員が対応します。解決をはかるために必要な助言や情報提供を行ったり、苦情処理のためのあっせんや適切な機関の紹介などを行っています。
最近では、悪質商法による被害が多く発生し、それを未然に防ぐために情報提供や啓発事業を実施しています。消費者力を身につけ、地域に広げることが大切です。
横浜市消費者総合センターにおける26年度上半期の相談件数は、12,320件で、前年同期より231件減少しています。相談件数の特徴は、すべての年代で、アダルト情報サイトや出会い系サイトなどの「デジタルコンテンツ」に関する相談が最も多くなりました。また、40歳以下の年代では、賃貸アパート退去時の敷金等に関する相談、60歳以上の年代では、「リフォーム」や「金融商品」に関する相談が多い傾向にあります。なお、60歳以上の年代の相談件数は4,037件で、全相談件数の約33%となっています。
国において平成24年に施行された「消費者教育の推進に関する法律」では、消費者について①被害に遭わない、②合理的意思決定ができる、③社会の発展に積極的に関与する自立した消費者の育成をめざしていくことが謳われ、各自治体において、消費者教育推進計画の策定が促されてきています。
横浜市においても、こうした動向の中で、高齢者の被害防止の視点も持ちながら、消費者教育を推進していく必要があると考えます。
そこで、こうした事を踏まえて、平成27年度予算委員会において、横浜市においても、高齢者の被害防止の視点も持ちながら、消費者教育を推進していく必要があるとの考えから消費者教育推進計画の策定をどのように進めていくのか確認しました。
これについては、横浜市独自の制度である「消費生活推進員による地域での活動強化」、「地域における消費者教育の推進による高齢者、障害者への見守り強化」する。
消費者教育推進計画については、現在、有識者や消費者団体等に意見を伺いながら、消費者教育の基本的な考え方となる「横浜市消費者教育推進の方向性」をまとめており、これを基に、毎年度、計画を策定するとの答弁がありました。
消費者被害を未然に防止するためには「消費者教育推進の方向性」を分かりやすく示していくとともに、特に高齢者については、高齢者本人だけでなく、高齢者を見守っている方への啓発が大切です。着実な取り組みが大切になります。
(写真は、道路の危険箇所へのカーブミラーの設置)